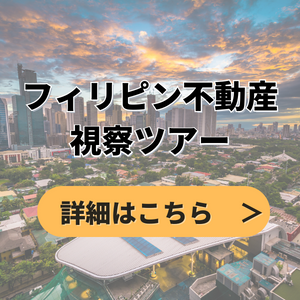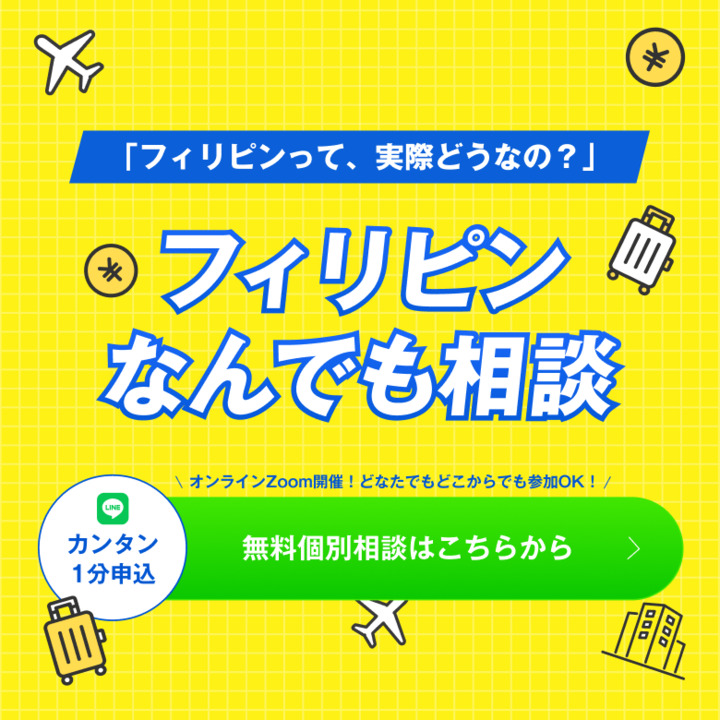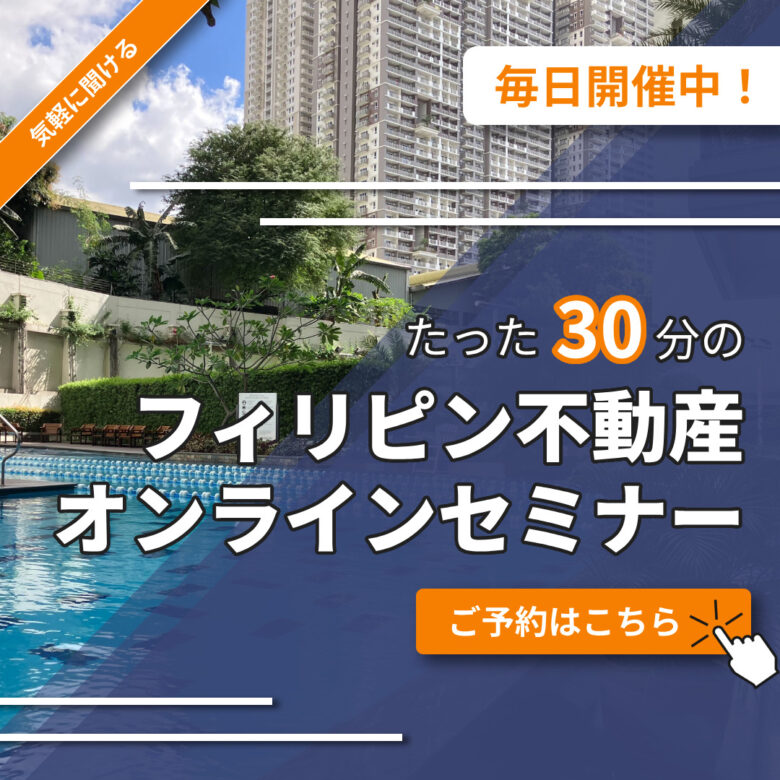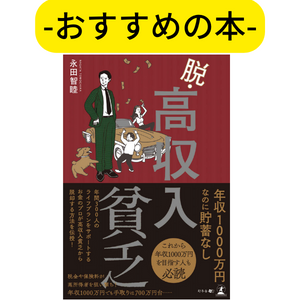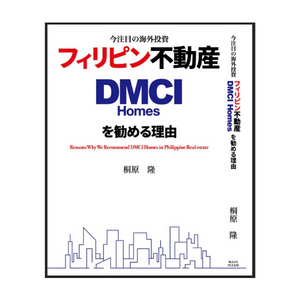フィリピンの銀行金利は、高い経済成長とそれに伴うインフレ動向、そしてフィリピン中央銀行の金融政策が複雑に絡み合い、預金者や借り入れを行う人々にとって重要な意味を持っています。
この記事では、フィリピンの銀行金利の現状と、その背景にある経済指標、さらに今後の見通しについて分かりやすく解説します。フィリピンの金融事情に関心のある方はぜひご一読ください。
目次
フィリピンの銀行金利の現状と展望

フィリピンの銀行金利は、近年、インフレ動向やフィリピン中央銀行(Bangko Sentral ng Pilipinas 通称BSP)の金融政策によって変動しています。高い経済成長と安定した金融システムを背景に、日本と比較して高めの金利水準を維持しているのが特徴です。
現在の政策金利(基準金利)
フィリピン中央銀行は、経済の安定と物価上昇の抑制を目的として政策金利を決定しています。
2025年4月10日時点では5.50%となっています。直近では2024年12月19日の5.75%から引き下げられています。
2025年の主な地域の政策金利
| 国名/地域 | 政策金利(2025年) |
|---|---|
| フィリピン | 5.50% (2025年4月) |
| インドネシア | 5.50% (2025年5月21日) |
| ベトナム | 3.00% (2025年2月) / 4.25% (2025年末予測) |
| 日本 | 0.5% (2025年5月1日) |
| アメリカ | 4.25%~4.50% (2025年5月) |
データ元: Trading Economics
過去の政策金利の推移
フィリピンの政策金利は、1985年から2025年までの平均で7.31%を記録しています。2020年11月には過去最低の2.00%まで低下しましたが、2023年10月には6.00%を記録するなど、近年は上昇傾向にありました。
預金金利の現状
フィリピンの預金金利は、日本の低金利と比較すると魅力的な水準にあります。
フィリピン中央銀行(BSP)は2025年5月時点で、夜間預金施設金利(Overnight Deposit Facility)を5.00%で据え置いています。これは銀行間の資金取引金利の下限であり、市中の預金金利の基準水準ともなっています。
具体的な預金の種類と金利の目安は以下の通りです。
- ドル建て預金: 経済情勢によって変動はありますが、ドル定期預金では1~2%程度が目安とされています。利息にかかる源泉徴収税は7.5%です。
- ペソ預金: ドル建て預金よりも高めの利率が設定される傾向にありますが、フィリピンペソの為替変動リスクを考慮する必要があります。利息にかかる源泉徴収税は20%です。
- 金融商品: 元本保証の長期商品や国債商品の中には、5~10%近い利回りを提供するものもあります。
フィリピンの貸出金利の現状
フィリピンの銀行貸出金利も、フィリピン中央銀行(BSP)の政策金利の動向に連動して推移しています。政策金利が引き上げられれば貸出金利も上昇し、引き下げられれば下落する傾向にあります。
2024年12月には8.036%を記録しました。
住宅ローンの金利は?

フィリピン不動産をローンで所有する場合、下記のローンがあります。
ただしプレビルドの場合、分割支払いでも金利は発生しませんので有効に活用しましょう。
インハウスローン(ディベロッパーからのローン)
インハウスローンは、不動産ディベロッパー自身が提供する融資形態です。融資期間10年間で金利12%ほどと高めですが、大きな審査も無く、どなたでもローンを組むことが可能ですので、まとまったお金がなく他のローンが組めなかった際に使用するといいでしょう。
バンクローン(現地銀行からのローン)
現地物件を担保に、融資期間10年間で金利6-7%程度とインハウスローンより低いですが、審査は多少厳しくなります。
しかし日本よりは厳しくなく、弊社としても多数実績がございますので気になる方は、一度ご質問ください。
フィリピン現地の不動産を担保にした現地ローンのご案内に加え、日本国内に不動産資産をお持ちの方には、日本国内での資金調達という選択肢もご提案可能です。
優先順位としては、国内ローン>バンクローン>インハウスローンで検討してみてください。
なぜフィリピンの金利は高いのか?

日本と違い、金利が高い背景には下記のような理由があります。
1. 高いインフレ率と物価安定の目標
最も重要な要因は、インフレ率の高さです。フィリピン中央銀行(BSP)の金融政策の主要な目標の一つは、物価の安定を図ることです。
インフレ抑制のための金利引き上げ
物価が上昇しやすい経済環境では、中央銀行はインフレを抑制するために政策金利を引き上げる傾向があります。金利を引き上げることで、銀行からの借り入れが減り、消費や投資が抑制され、結果として物価上昇の勢いを弱める効果が期待されます。
実際、2022年のウクライナ侵攻による原油価格や食料品価格の高騰、国内の供給要因などにより、フィリピンのインフレ率は一時的に急加速しました(2023年1月には8.7%に達しました)。これを受け、BSPは急ピッチで政策金利を引き上げてインフレ抑制を図りました。
実質金利の維持
預金者が預金することのインセンティブを維持するためには、名目金利がインフレ率を上回る、あるいは少なくとも同程度である必要があります。そうでないと、実質的な購買力が時間とともに低下してしまうため、預金者は銀行にお金を預けようとしなくなります。したがって、高インフレの国では、名目金利も高くなる傾向があります。
2. 経済成長と資金需要
フィリピンは近年、高い経済成長を続けている国の一つです。
経済が成長する局面では、企業は設備投資を増やし、個人も消費を拡大する傾向があります。これには資金が必要となるため、銀行からの借り入れ需要が高まります。
また、資金需要が高い状況では、銀行は高い金利を設定しても資金を貸し出すことができます。需要と供給のバランスが金利水準を押し上げる要因となります。
3. 海外からの資本流出抑制
国際的な金利差も、フィリピンの金利水準に影響を与えます。
特に米国の金利動向は、新興国の金融政策に大きな影響を与えます。米国が金利を引き上げると、より高いリターンを求めて資金が新興国から米国へ流出しやすくなります(資本流出)。
資本流出が起こると、自国通貨(フィリピンペソ)が売られ、通貨安が進行する可能性があります。通貨安は輸入物価を押し上げ、さらなるインフレを招く恐れがあるため、BSPは資本流出を防ぎ、ペソ安を抑制するために高めの金利を維持する場合があります。
4. 開発途上国としての特性
一般的に、開発途上国や新興国は、先進国に比べて金利が高くなる傾向があります。
経済の変動リスク、政治的な不安定さ、信用リスクなどが先進国に比べて高いと認識される場合、投資家はより高いリターン(金利)を求めるため、「リスクプレミアム」として金利が高めに設定されます。
金融市場がまだ発展途上であることも、流動性の低さから金利を押し上げる要因となることがあります。
これらの要因が複合的に作用し、フィリピンの銀行金利は日本などの先進国と比較して高めに推移しているのが現状です。
日本も過去にそうだったようにフィリピンもまだ発展途上と言えるでしょう。
フィリピンの金利の今後の見通しは?

Trading Economicsのグローバルマクロモデルとアナリストの予想によると、フィリピンの基準金利は今四半期の終わりまでに5.50%になる見込みです。
長期的には、夜間預金施設金利は2026年に約4.50%、2027年には4.25%の水準に推移すると予測されています。
インフレ率も2026年に約2.50%、2027年には2.40%へ推移すると予測されており、金利とインフレ率のバランスを見ながらの政策運営が続くでしょう。
まとめ
フィリピンの銀行金利は、日本の現状と比較しても非常に高い水準にあり、資産形成の観点から注目されています。海外の金融サービスに目を向けることは、リスクと隣り合わせであると同時に、新たな可能性でもあります。
選択肢を知り、情報を集め、自身に合った形で活用していく。そうした一歩が、これからの時代における新たな資産戦略につながるかもしれません。